受注からスケジュール作成まで
進行管理にとって、仕事を受注したあとの最初の大仕事は「スケジュールを立てること」だ。
ここでの設計が、その後のすべてを左右すると言っても過言ではない。
スケジュール作成で大切なのは、まず理想形を組むことだ。
クオリティ、納期、作業効率、リスクヘッジ――これらすべてをバランスよく満たすために、無理のない作業スパンを想定して組む。
この「理想」をまず組むことが、仕事のベースになる。
だが、現実にはこの理想形がそのまま走り続けられることは稀だ。
だからこそ、最初のスケジュール設計時点から、ズレた場合のリスクヘッジも視野に入れておかなければならない。
スケジュール通り進まない現実
どんなに綿密にスケジュールを立てても、予定通り進むことのほうが少ない。
これは進行管理なら誰もが経験している現実だ。
- クライアントの修正指示が遅れる
- 予想外の追加案件が発生する
- 社内リソースが別案件に取られる
- 承認プロセスで想定外に時間がかかる
一度遅れが生じると、ドミノのように後工程にも影響が広がる。
ここで必要になるのが「リスケジュール」だ。
リスケのとき、理想は当然、最初と同じスパンの時間を確保することだ。
作業時間を無理に縮めると、クオリティ低下・ミス・納期遅延のリスクが爆発的に高まるからだ。
だが――
現実は、同じスパンを確保できないことがほとんどだ。
理想と現実のギャップを受け入れる
ここで進行管理が陥りやすい落とし穴がある。
「どうしても同じスパンが欲しい」と粘りすぎて、空気を悪くしてしまうことだ。
本当は、最初と同じ時間を確保できれば理想的だ。
だが現実には、納期は動かせない、他案件の都合もある、クライアントも待っていられない。
そんな状況が重なって、どうしても短縮せざるを得ない局面がある。
ここで大事なのは、現実を受け入れる覚悟だ。
「本来ならこれだけの時間が必要だけれど、今は事情が違う」
「理想じゃない。でも、できる限りのリスクヘッジをして、ベストを尽くそう」
そう考え直し、次の一手を打つ。
これが、プロの進行管理だ。
営業やお客様への伝え方 ~共感ベースで話す~
理想通りの時間が取れない時、どう営業やお客様に伝えるか。
ここに進行管理の腕が問われる。
正論だけを押しつけるのは逆効果だ。
たとえば、こういう伝え方をする。
「本来なら3日間は最低でも欲しい工程ですが、今回状況が状況なので、1.5日でできる最大限の対応を組んでいます。ただ、通常よりミスリスクや仕上がりに影響が出る可能性が高くなることは、正直にお伝えしておきます。」
ポイントは、
- 相手の状況を理解していることを前提に話す
- 無理を押しつけるわけではなく、リスクを共有する
- 味方のスタンスで話す(責めない)
共感をベースにすると、営業もお客様も心情的に納得しやすくなる。
この「対立しないコミュニケーション」が、後々大きな信頼につながる。
それでも縮まったスケジュールで動くときの心構え
短縮されたスケジュールで進めるときは、リスクを前提に行動することが大切だ。
- 確認作業は普段以上に厳密に
- 記録を残す(やり取り・変更履歴)
- 事前に「ここがリスクポイントです」とチーム全員に周知
- クオリティ担保できない場合のエスケーププランも用意しておく
何も起きなければそれでいい。
だが、何か起きた時に「想定していた」と対応できるかどうかが、進行管理の力量だ。
【まとめ】進行管理は現実を受け入れ、最善を尽くす職種
進行管理の理想は「無理のないスケジュールで完遂すること」。
でも現実は、理想通りに進められない局面が必ず出てくる。
そのとき、
- 理想に固執せず現実を受け入れる
- 共感をベースに、営業・お客様とリスクを共有する
- 与えられた条件の中で最善を尽くす
この姿勢を持ち続けることが、
「仕事ができる進行管理」と言われるために欠かせない条件だ。
進行管理は、戦う職種ではない。
現実を受け入れ、みんなをゴールに導く役割なのだ。
まとめページはこちら
→進行管理の仕事とは?広告業界の働き方と未来を変える方法<全3回 まとめ>
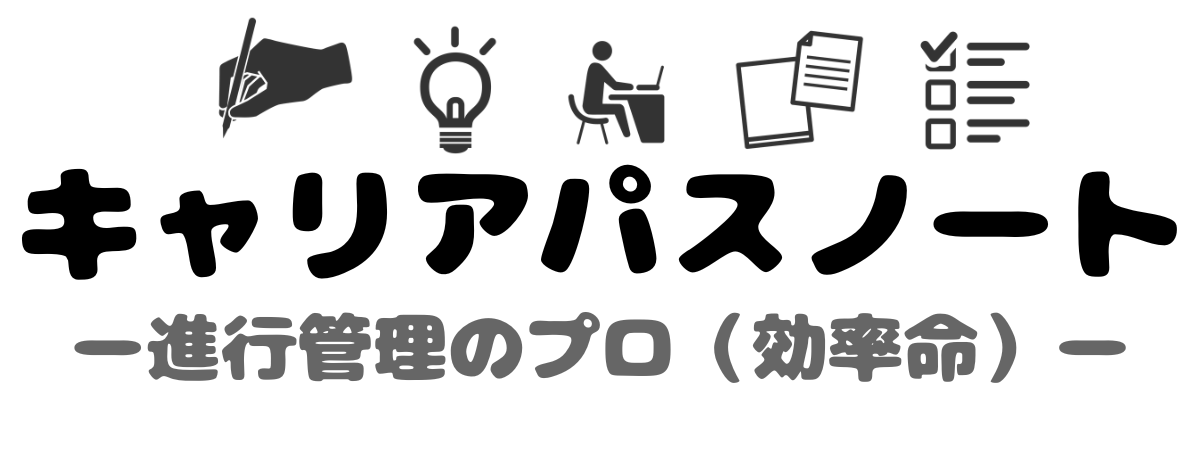










コメント